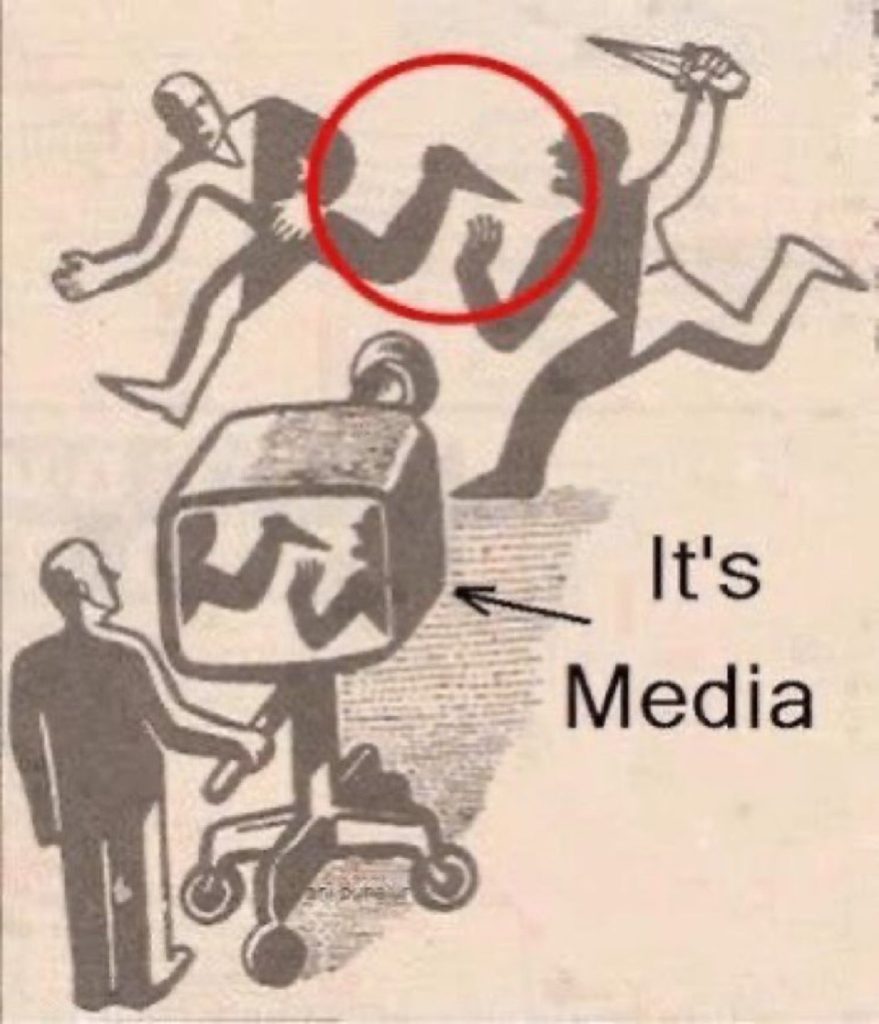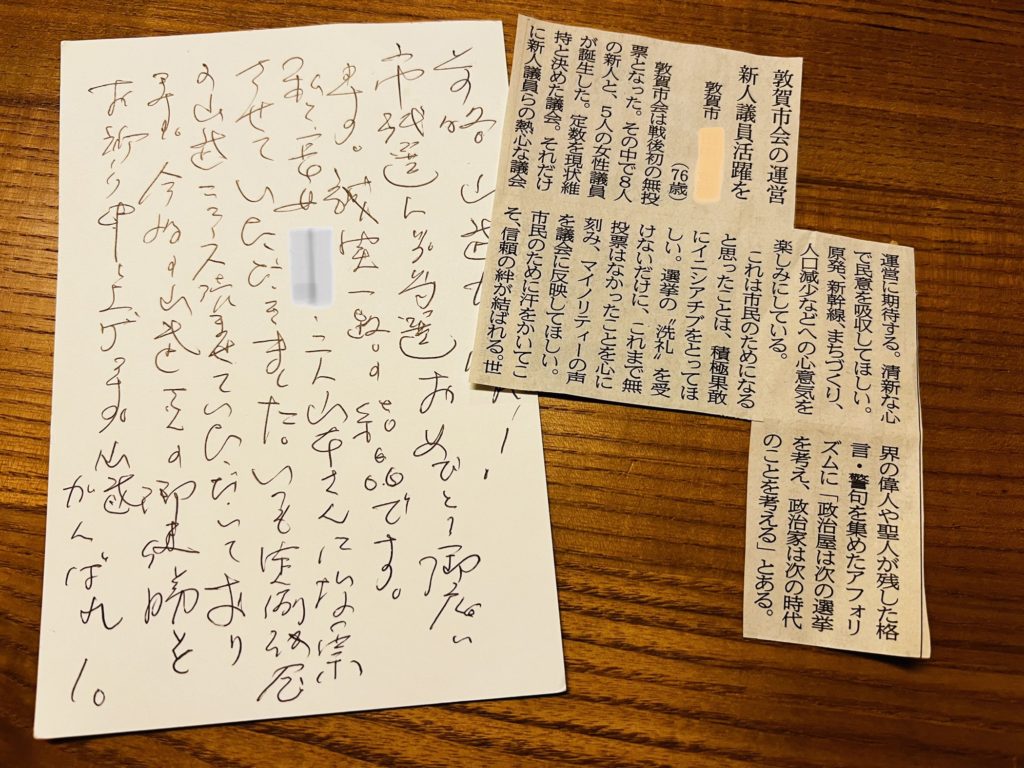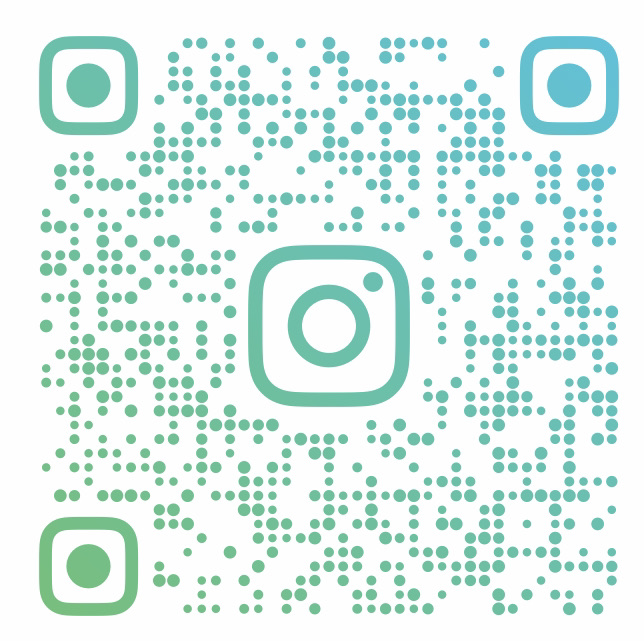2024年6月29日
前進できぬ駒はない
3期9年に亘り敦賀市教育長を務められた上野弘氏が退任。
先般ご紹介した通り、上野前教育長は私が粟野中学校3年生の時、同学年別クラスの先生であったことから、かれこれ35年以上前に知り合ったことになりますが、任期満了となる昨日、教育長室にお伺いし、暫し歓談させていただいた後、最後のご挨拶をしたところです。
子どもの教育環境はもとより、文化芸術やスポーツの振興まで幅広い分野を所管する教育委員会において、トップリーダーとして取り組まれた“上野先生”に、改めて感謝と敬意を表する次第です。
市内にお住まいですので、またお会いすることもあろうかと思いますが、今後はくれぐれもご健康に留意され、新たなステージでご活躍されますことご祈念申し上げます。
また、この6月は母体の日本原電では人事異動時期。
ここ敦賀の地から転勤される方や退職される方にとって昨日は現職場での最後の出勤日。
お世話になった方すべてに直接お声を掛けることまでできませんでしたが、皆様方におかれましては、これまで献身的に業務にあたってこられたこと、また私の活動に対してもご理解とご協力をいただいたことに心より感謝するところ。
それぞれ、新天地あるいは別の分野での飛躍を祈念する次第です。
なお、転勤や退職は仕事のみならず、人生における大きな転機であることはいうまでもないところ。
この機会を前向きに捉えられる方もいれば、不安にかられる方もいらっしゃると思いますが、皆さんに贈りたいのはこの言葉。
「前進できぬ駒はない」
これは、昭和から平成の時代にプロ棋士として活躍した十六世名人の中原誠さんが語った言葉で、歩や桂馬、香車のように、将棋の駒の中には後退できない駒がある一方で、前進できない駒はないんだということを意味しています。
真っすぐ1歩ずつ進んだり、斜めに進んだりと、駒ごとに動き方はさまざまですが、それでも確実に前へと進める。
これは将棋盤の上だけに留まらず、私たちの人生においても言えることであり、転機や日々の行動すべてが「前進」につながると思えば元気、勇気が湧いてくるもの。
私自身もこの言葉を胸に置くとともに、週明けから新たなスタートを切られる皆様にエールを贈る一言になれば幸いです。

【もう一言エールを。「この道を行けばどうなるものか。 危ぶむなかれ、危ぶめば道はなし。踏み出せばその一足がみちとなり、その一足が道となる。 迷わず行けよ、行けばわかるさ。」byアントニオ猪木(写真は6月27日やまたけ撮影)】