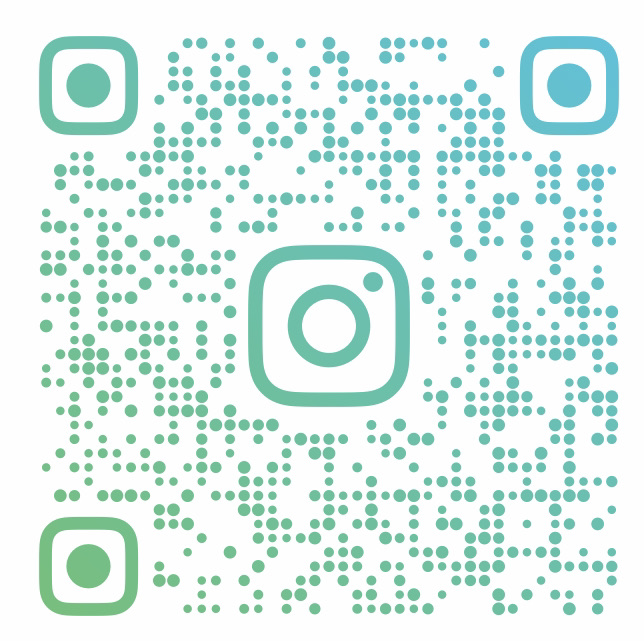2024年7月27日
敦賀2号は今後も「稼働に向けて取り組む」
4時間近くに及んだ、昨日の敦賀発電所2号機に関する原子力規制委員会(以下、規制委)の新規制基準に係る審査会合(第1272回)。
K断層の「連続性」を論点に、日本原電からの説明の後、質疑が繰り返されましたが、結果、「不確かさ」「曖昧さ」等を挙げ、規制委として従来の考えを変えることはないとのこと。
また「活動性」に関しても日本原電から再説明がされものの、こちらも同じく「可能性を否定することは困難」との答えは覆らず。
なお、日本原電からは、これまでの調査・データで明らかにできていないこと、審査会合における規制委のコメント等を踏まえ、追加調査並びに再補正申請についても言及、申入れがされ、これらのことも含め、次週7月31日(水)の原子力規制委員会に審査の結果として報告されることとなりました。
これを受け、日本原電は以下のコメントを発表していますのでご覧ください。

【7/26 日本原電プレスリリースより】
敦賀2号審査を巡る、昨日から今日に掛けての報道を見ると、「廃炉を迫られる可能性」「廃炉となる可能性が高い」とのタイトルでセンセーショナルに記載されていますが、一体誰が「廃炉」を決めるんでしょうか。
7月24日に原子力規制員会の山中委員長も会見で述べている通り、あくまでも「廃炉は事業者の判断」。
当の日本原電は、上記のコメントにもあるよう、これまでの審査会合や現地調査での議論を踏まえ、今後も追加調査やデータの拡充をし、「稼働に向けて取り組む」としています。
審査会合の場で規制委のコメントに反証仕切れなかった以上、それが「悪魔の証明」であったとしても、規制委が言う「可能性を否定することは困難」を「可能性を否定」に、「不確かや曖昧」なものを「確かな」ものにし、「活断層ではないこと」を立証するのは他ならぬ日本原電であり、何としてでも今後の追加調査で明らかにしていただきたい。
次の注目は、7月31日の原子力規制委員会となりますが、審査チームからどのような報告がされるのか、日本原電が申入れたことが受け入れられるのかを見守る次第です。
(参考)
敦賀2号の審査不合格、廃炉の可能性ばかりが報じられるなか、産経新聞の論説「主張」はド「正論」でしたので、以下にリンクいたします。
→<主張>敦賀原発2号機 初の不適合は理に合わぬ 規制委は審査の継続に道開け(2024年7月27日 産経新聞)