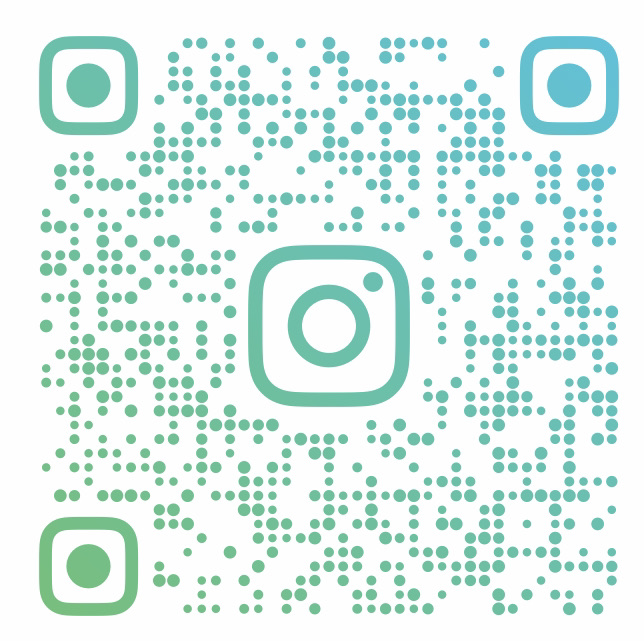2024年6月19日
敦賀発電所2号機の審査に係る「多くの疑問」
敦賀以西は「小浜・京都ルートしかない」。
昨日注目の、北陸新幹線の大阪延伸を議論する与党の整備委員会で、敦賀から先は現行の「小浜ルート」を堅持し、2025年度の着工を目指すと改めて確認。
石川県の一部関係者などから、東海道新幹線の米原(滋賀県)につなぐルートへの再考を求める声が上がるなか、与党の姿勢を明確にするとともに、西田昌司委員長(参議院・京都府選出)は会合後の取材で「米原ルートは、システムや東海道新幹線の容量の問題がある」と述べ、再考を否定しました。
会合では、来年度着工に向け、年内に駅位置などを含む詳細を決める方針を共有したともあり、いよいよ敦賀以西の計画が具現化することを期待する次第です。
さて、北陸新幹線開業は、ここ敦賀にとって「歴史の転換点」となった訳ですが、産業基盤という観点からも、地元にとって欠かせないのは「原子力」。
先のGX実行計画にあった「最大限活用」を踏まえ、さらには電力需要が増加予想の中で迎える次期「エネルギー基本計画」見直しにおいて、「原子力発電」は将来に亘るベースロード電源として明確に位置付けられるべきと考える次第ですが、日本原電の敦賀発電所2号機(敦賀2号)もその一助を担うべく、早期の再稼働が待たれるところ。
敦賀2号に関しては現在、原子力規制委員会の審査が進められており、状況はこれまでもお伝えしている通りでありますが、ある方からのご紹介で関連記事が掲載されていることを知りました。
その記事とは、国際環境経済研究所理事・主席研究員の竹内純子(すみこ)氏が,敦賀2号審査(共同通信記事)について「NewsPicks」に投稿したもので、有識者からの本質を捉えたご意見と拝見いたしました。
こちらは皆様とも共有できればと思い、以下記事を引用掲載いたします。

【敦賀2号審査において「活動性を否定できる地点ではない」とされた「D-1(破砕帯)トレンチ」はこれほどまでの調査規模(2023年12月1日の視察時に許可を得て撮影)。】
<以下、竹内純子氏の記事引用>
原子力規制委員会の行政機関としての活動に、かなり課題があることは以前から繰り返し指摘していますが、日本原電への審査活動を詳細にみると、多くの疑問が出てきます。
まず、審査活動の頻度ですが、敦賀2号機の審査は、2023年9月以降、9ヶ月で6回の審査会合と現地調査、現地確認が実施されるなど、他地点と比べ短期間に集中しているように思えます。手厚く審査している、と言うことかもしれませんが、事業者側が規制委員会の宿題に応えるには時間もかかるので、短期間に審査を集中させた理由を聞きたいところです。
断層の活動性と連続性を並行で審査するとされて、連続性については、3月の審査会合で日本原電側から説明、4月現地確認、6月と7月の審査会合でコメント回答という同時並行という慌ただしさ、6月6、7日の現地調査では、連続性のコメントを当初の回答予定時期より早めて7月中旬までに回答するよう求めたようですが、ここにきて何を急に急いでいるのか。
新規制基準への審査については全般的に時間がかかりすぎているのは事実ですが、ここにきて急に半月、1か月を急がせるというのは、何かあるのでしょうか?
また、5月で確認は終えた、と規制委員会側から議論打ち切りととれる通告があり、事業者としては、追加調査の結果など説明の継続を主張したとのこと。規制委員会は、「事業者が追加調査を実施するのは否定はしないが、確認は終了したという姿勢を崩さなかったようです。「事業者が追加調査を実施するのは否定はしないが」というのはずいぶんな言い草で、行政機関としての規制委員会に対して、国会がきちんとガバナンスすべきことを示しています。米国の原子力規制では、議会が規制委員会に対してきちんとチェック機能を果たしています。
よもや国会閉会中にこれほどの重大な決定がされることはないと思いますが、この不安定な国際情勢の中で、エネルギーという生命線を確保する上で、極めて重大な判断であり、政府・国会でもきちんと議論していただきたい。
自民党の「原子力規制に関する特別委員会」が以前出された安全規制に関する提言は極めてよく考えられたものでしたが、改めてあの提言を活かして、より良い規制活動にしていただくことを祈ります。
<引用終わり>
立場上、これ以上言及することは控えますが、米国の原子力規制と日本とで大きく異なるのは「経済合理性」や(独立性の高い第三者委員会であるが故の)「議会との関係」。
皆様におかれましても、この分野の第一人者とも言える竹内氏の「多くの疑問」を胸に留めていただければと存じます。